|
昭和48年(1973年)普通の合唱団としての誕生でした。
そしてしばらくは順調に成長していったのですが、ある頃から、日本語を日本語とした表現をもっときちんとしたいという欲求が生まれ、日本の唄、日本の言葉へのこだわりが始まります。 また同じ頃、指揮者が聴衆と、歌い手の間にいること、楽譜に視線をとらわれていることへの疑問も生まれました。
そして、演劇集団との出会い。発声練習から始まった、演劇の人たちとの関わりの中で発声だけでなく所作(動き)への挑戦も始まります。 このころ現在の混声の基本ができ始まります。そして発声面でも、日本語は、日本語の。日本の唄は、日本の唄の発声も要求され始めます。しかし同時にこのことは、従来の合唱から離れられない人々との決別も生んでしまいました。残った人々にとっても従来のものと違った合唱づくりは大変で、とりわけ半ば出来上がった発声を代えることは大変な努力を要求されました。
上田混声合唱団からVPG上田混声合唱団へ更に信州国際音楽村合唱団VPGへと変遷を重ねます。そして迷走の中、現在の形がありますが、今もまだ、自分たちの音楽を求めて、試行錯誤の途中です。
VPGはヴォイス・パフォーマンス・グループ(造語)の略です。
合唱団だけでは自分たちの活動内容が十分伝えられないので、冠をつけました。 当然歌うだけでなく理想としては、踊ったり芝居もできるようになりたい、いろんな
表現を取り入れたいと思っています。
唄に貴賤なし
ブルガリアンボイス・グルジアンボイス・日本民謡・唱歌・ポピュラーからジャズ・ゴスペル・更にオペラまで歌う歌のジャンルはこだわりません。自分たちが歌いたいかどうかだけです。
当然歌にあった発声を使い分けようとしています。
指揮者を置きません 楽譜も持ちません
聴衆と歌い手の間に指揮者を置かないことで歌い手の息づかいが直接聞き手に向けら れます。同じ意味で楽譜も持ちません。 リズムは、耳を澄まして、歌い手同士の息使いで合わせます。
合唱は自己主張 お互いを聞き合って人を大事にして歌いますが、その上で全員が外に向かって、同じ 緊張度で自己主張しています、丁度大きな風船を作っているようなものです。一人が
力を入れすぎても、抜きすぎても風船(合唱)は崩れてしまいます。
団の運営は合議制
当団には、偉い先生がいません。従って提案事項について代表があらかじめ相談することはありますが、基本的に団の決定事項は団員全部の合議を基にしています。
発言に関しては誰でも対等です。誰かの提案に、特に反対がなければ決まるし、反対があればそれについて皆で相談します。
演奏会の運営も毎年、新人、経験者を問わず、選ばれたメンバーがプロジェクトを編成して皆の先導役になります。
ステージは
公民館、市民会館、地区の公民館、教会、レストラン、お寺の本堂、信金ギャラリー、信州国際音楽村こだま・ひびき、図書館ライブラリー 等々
共演の人々 (敬称略)

ブルガリアンヴォイス |
|

日本民謡 |
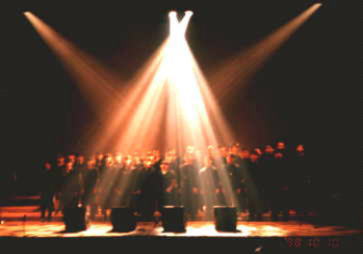
ゴスペル |
|

ポップス |
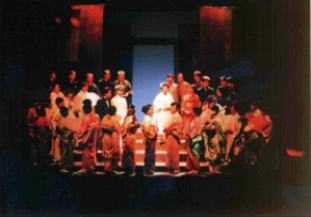
オペラ |
|
プロのミュージシャンから
地元のアマチュア団体まで
故・三瓶十郎先生と長野室内楽協会
長野上田マンドリン・アンサンブル
劇団「憑依」
民謡・原田直景会
寺内タケシとブルー・ジーンズ
戯曲家・故・秋浜悟史
作曲家・三木稔
日本音楽集団有志
上田モナミ合唱団
いけないシスターズ
呉恵珠
丸子混声合唱団
音楽村児童合唱団
タイムファイブ
クミコ
小室等
八木のぶお
藤田傳
佐藤允彦
ウォン・イルとパラムッコ などなど
演奏曲集 団の歴史  メール メール
|